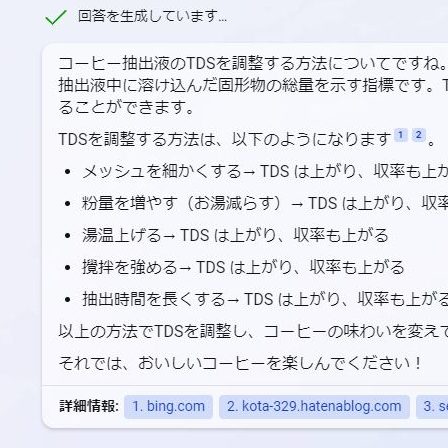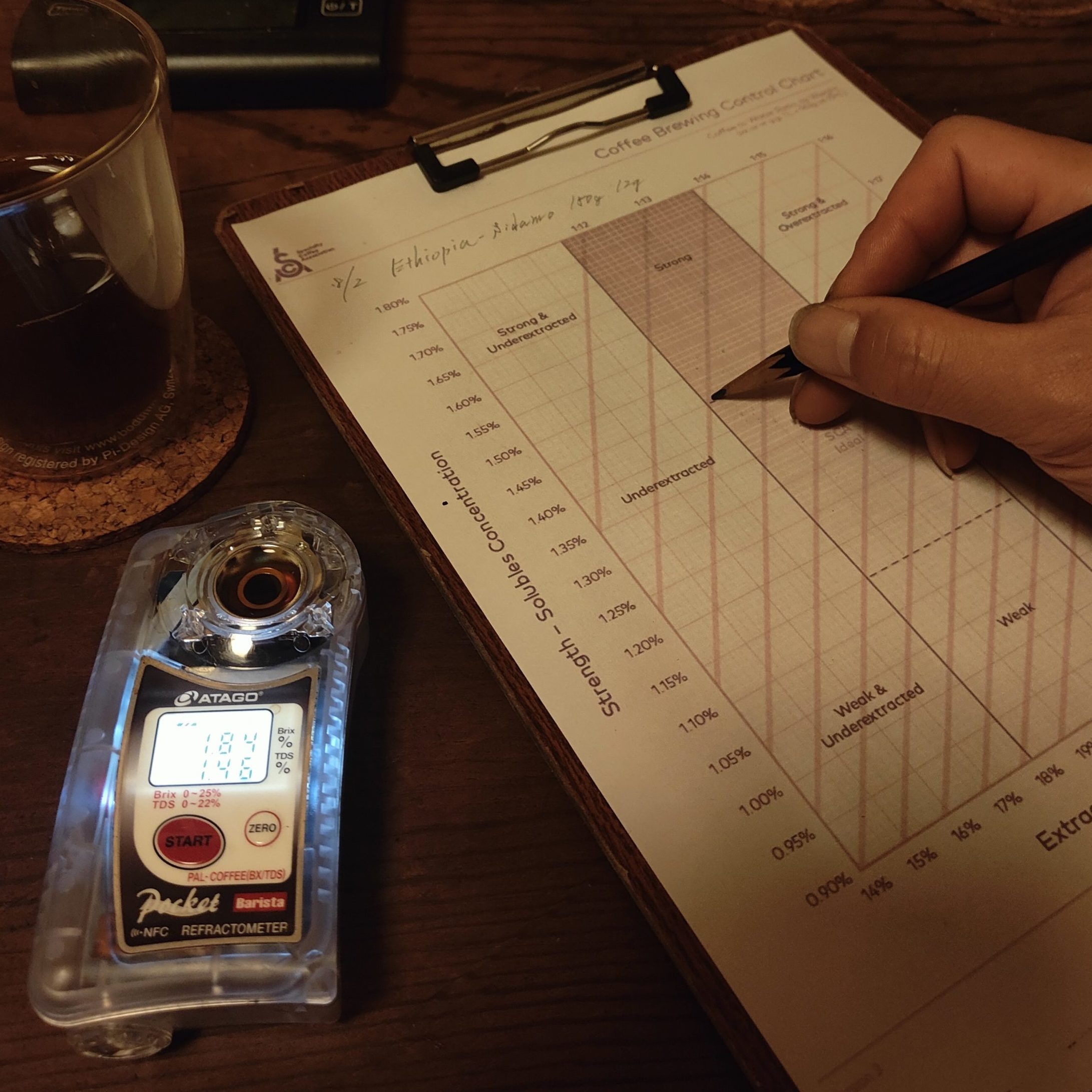Q&A
どなたでもどこでも美味しいコーヒーを
コーヒーの入り口はどこから?
当店は10年以上に渡り様々な場所で何十万杯というコーヒーをお作りすることを通じて、多くのお客様と直接お話させてもらって来ました。
その中でも頂く機会の多いご質問やご要望について、店頭では十分にお答え出来ないポイントを含めた回答をまとめています。
- 思うようなコーヒーに出会えない・作れないんだけど?
- 自分で淹(い)れてみたいけど難しくない?
- どれが良い悪いと言われても、どこがどう違うの?
- もっと深くコーヒーについて学びたい
- アウトドアでも自由にコーヒーを楽しみたい
回答に当たっては「どなたでも・どこでもお好きなコーヒーを楽しめるように」という当店のコンセプトに沿って、あらゆるコーヒーに通じる優先度と信頼性が高い情報に絞ってお伝えするよう心掛けています。
また、抽出ノウハウとしてのの難易度は当店基準で中級段階まで。焙煎ノウハウについては現在の所は非公開としています。
当店が営業において実践している方法は、「野外イベントでのコーヒーサービス」という特殊な環境に最適化して来たものですが、それは、私たちやコーヒーを形作っている「自然の働き」を生身で感じながら得て来た知見に則っています。
日常的なコーヒーに関する情報は、自ずと多数派の需要に偏ったものが支配的になって行くために、どうしても「自然法則」という視点が埋もれやすくなってしまいます。
私たちの身の回りの暮らしを形作る物や働きを生み出している根拠(源流・ソース)の喪失は、様々な疑問や混迷に陥る根本的な原因を生み出します。
このような理由から、当店のQ&Aではあえて、豆・焙煎・抽出・器具・お店といった形で源流から無数に枝分かれした末端にフォーカスを当てたレビューやハウトゥー、宣伝を中心とする解説とは一線を画すように配慮しています。
ご自身の力で目的とするコーヒーに辿り着いて頂くためには、支流の細かい流れを追い続けて右往左往する道のりよりも、根本にある源流(原理的な仕組み)へと足場を固めながらさかのぼって行く道のりの方が、結果的には確実でシンプルな選択となるからです。
こうした当店の考え方は、コーヒーだけでなく人々の暮らしを生み出す源流「杣(木々や水、土を育む山々)」に思いを馳せて付けた屋号に至るまで一貫するものです。
現代の日本においては、品質の高いコーヒーを淹れるために必要な材料・労力・費用に関する障壁は存在しない、と断言出来るほどに恵まれた環境が誰の前にもすでに整っているように感じます。
にもかかわらず、以下のような心理的なイメージや予備知識によって距離を置いてしまわれたり、迷い道や落とし穴にハマってしまわれたりするケースが未だ少なくありません。
- コーヒーは奥が深い・難しい
- こだわりの~・職人の~・厳選された~・極上の~
- 違いが分かる~・大人の~
近年のコーヒー業界は情報と物流ネットワークの発展によって、まさに当店もそうであるように、趣味の延長からでも始められるほど参入障壁が低くなっている分野の一つに挙げられます。
しかしながら、歴史的なものも含めたマーケティングやブランディング戦略によって培われて来たイメージと実際の状況の間に大きなギャップが存在することも確かなようです。
私たちが日常的に触れられる範囲のコーヒーは、特殊で高度な知識や技術、および感性がないと楽しめないものでは決してありませんし、むしろその逆ではないかと思います。
それぞれの方が抱く「コーヒーのイメージ」とは、どこからどのように生まれるものなのでしょうか?
大なり小なりはあるとしても、そこにギャップが生まれてしまう原因には、以下に代表されるような情報伝達に関わる問題が潜んでいます。
- 一部分、一面のみが切り取られている
- 無関係なものがバラバラに組み合わされている
- 主張・宣伝・誘導に利用されている
- 実体と付加価値の乖離
その発信源には市場の仕組みが存在し、次々と生み出されては消え続ける混濁した情報の波が、すでに私たちを飲み込んでしまっている状態にあります。
この状態こそが、そうとは気付かぬうちに私達が本来望んでいる道のりを阻む最も避け難い障壁になっているのではないか?とさえ感じるほどです。
コーヒーの入り口は至る所に見つかる現代、いつの間にか迷い道や落とし穴に誘い込まれて苦しむことのないように、目的地までの具体的なガイドラインをお示しする「地図とナビゲーション」としての役割を担うことが、このQ&Aで目指していることです。
外から見えて来るコーヒーの新しい地図
皆さんご存じのようにコーヒーには長い歴史があり、豆、器具、工程、お店などのそれぞれに目を向ければ多種多様な楽しみ方があります。
では、そういった中からご自身のお好みのコーヒーにたどり着くためには、誰もが以下のような険しい道を進む必要があるのでしょうか?
- 一つ一つの豆や器具、お店、手法の特徴や仕組みについて一から十まで網羅する
- インターネットや本を始めとするメディアの情報を手当たり次第に読み漁る
実は、これらに掛けるコストや心配は必要不可欠というものではありません。
さらに言うと、学習の効率性という観点だけで見た場合には、むしろ非効率的な選択と言えます。
一つ一つのコーヒーやそれに関わる事柄にはそれぞれに貴重な個性がありますが、それらは全く別々のものでもなければ、人やお店といった個々の力だけで作られているものでもありません。
自然環境や地域、時代、文化、学問、テクノロジー、ビジネス、人々とその嗜好などに合わせて、少しづつ確立されて来た大きな土台の上に成り立っているものなので、それらの基本的な仕組みやつながりから紐解いて行けば、ある程度は同じカテゴリーやパターンごとに整理することが出来るからです。
その視点に立つことさえ出来れば、「コーヒー作りのパターン(道のり)はそれほど多くない」という全体像(地図)が見えるようになるので、盲目的に右往左往する必要もなくなります。
- なぜそうなっているのか?
- 全てに共通するポイントは何か?
これらの核心(原理)とそこに至る近道(法則性・パターン)に当たる情報は、この世界にすでに存在しています。
コーヒーのことが知りたくてコーヒーの世界だけを探していると、前述の理由によって返って見つかりにくくなってしまうかもしれません。
しかし、コーヒーも自然や私たちの暮らしの一部と捉えてみると、はるかに膨大で深遠な探究とその答えが多くのことを伝えてくれていることに気が付きます。
お好みのコーヒー(目的地)に辿り着くためには、次の行動を最優先にすることをお勧めします。
- 全体を見渡せる地図を得ること
- その中でご自身の現在地と目的地をつなぐ道を探し出すこと
なぜなら、生身の私たち一人一人の知識や感覚は常に局所的で不完全なものなので、「木を見て森を見ず」という行き当たりばったりの判断に陥いりやすく、いつどこで道を見失ったとしてもおかしくない状態だからです。
以下のコンテンツは、コーヒーに関する核心的な情報とそれらのつながりにフォーカスしてまとめるようにしています。
- 多種多様なコーヒーが生み出されるまでの全体像と原理的な仕組み
- ドリップ上達を目指す各段階で障壁になりやすいこととそれを乗り越える方法
- 未だよく分かってない謎についてと当店なりの探求
まだまだ拙い地図と思いますが、コーヒーをより自由に楽しんでもらうお役に立てば幸いです。